――『鼻下長紳士回顧録』(以下、『鼻下長』と略記)は二〇世紀初頭のパリが舞台ですよね。以前、安野さんにポショワールのお話を伺いましたが、それも二〇世紀初頭のファッションプレートでよく使われた技法でしたね。バルビエの絵とか。
安野 あの時代のファッションプレートは、今のファッション誌に当たるものですからね。
今季の新しいモードをあれで配っていた。商業と美術の融合ぶりが私の好みなんです。だって、お洋服が素敵でも売れなかったらしょうがない。ただ洋服だけを描けば良いわけではなくて、お洋服を含めたシチュエーションを素敵に描いて、「こんな風になりたいわ」と女の人に思わせなきゃダメでしょ。そのバランスが私のやりたいことに近いんです。
――全体的なデザインも素敵ですね。
安野 あの時代の洋服が好き、ということもあると思います。なぜ良いかというと、あの時代までは全部手縫いなんですよ。人が裁断して手で縫った服というのは、着た時の立体感、フィット感がぜんぜん違う。昔の写真が素敵に見えるのは、貧乏な人でも、着ている上着は人が縫ったものだからだと思います。私たちは普通、機械で縫った大量生産の服を着ているじゃない? 気軽に着られるし、良いところもいっぱいあるんだけど、やっぱり何か違う。言葉ではうまく説明できないけど、絵にすると変わってくるんですよ。家具もそうだし、室内にあるものも全部そうだと思う。だから、絵としてはそういうものを描いていきたいと思います。
――あと、ポショワールで描かれたファッションプレートは、シルエットで見せるようなスタイルで、ポップな面もありますよね。それは漫画と親和性がある気がします。
安野 省略して見せる感じでね。少女漫画家たちも影響を受けていると思います。バルビエを好きになって、改めて見てみたら、「私が子供の頃に好きだったこの先生のイラストは、ここからインスピレーションを受けていたんだ」と思ったものがいっぱいあります。あと、日本の叙情画もかなり影響を受けていると思う。構図とかバランスもね。ただ、もともとバルビエたちは浮世絵の影響で生まれたものなんですよね。それを、また日本人が良いと思って取り入れる。文化交換というか、循環している感じがありますね。
――面白いですね。今はまた、日本の漫画が世界に影響を与えていますし、本当に循環していると思います。バルビエといえば、『鼻下長』に協力としてクレジットされている鹿島茂さんはバルビエのコレクターで評論も書かれています。安野さんは鹿島さんと対談もされていますが、どんな刺激を受けましたか?
安野 鹿島先生は尋常じゃないお金を古本に使っているんですよ。たくさんエッセイを書いているけど、それも全部古本を買うためですから。そういう「やり切り感」に、私は昔の世代の人の凄さを感じる。今でもオタクのコレクターはいるけど、古本の場合は買うことにも技術が要りますよね。お金さえ出せば誰でも買えるわけじゃなくて。古本屋の主人との駆け引きも必要。いつも良い本を買って「さすがだね」と思われているからこそ、次に入荷する特別な本を教えてもらえたりする。長年の積み重ねもあるんですよね。そうして買った本をたくさん読んで、自分の家の裏庭のようにパリのことを語っておられる。漫画を描いていて苦労するのは、その世界観をいかに構築するか、ということなんだけど、絶対的な知識量があれば描けますよね。「鎌倉の物語を描きましょう」となった時に、今の鎌倉の生活なら描けると思うんです。でも、鎌倉幕府の歴史を踏まえて描けるかといったら難しい。そういう時にほころびが生じると、読者の人にも伝わりますよね。その点、鹿島先生は「もう良いですよ」というくらいの知識があるんです。そういう人が書いた本にはあふれ出る情報量があって、ちょっと読んだだけでも相当な栄養をもらうことができる。私もそのおかげで『鼻下長』を描けているんだと思いますね。
――安野さんは、娼婦の生き方とビジュアル面の両方に興味があって今回の『鼻下長』を描かれたんでしょうか。
安野 そうですね。結局は、今と何も変わらないんですよ。若い女の子がおしゃれをしたい、美味しいものも食べたい、といった時に、働けなかったらやることは一つ。それは古今東西どの国でもそうなんだけど、私は今の日本とすごくカブるな、と思った。生活苦で売春をする子もいるんだけど、ただ贅沢がしたくて売春をする子もいる。当時のパリでは、お洋服屋さんの女店主が手引きをしたのよ。今だったら、セレクトショップで「あー、このマーク・ジェイコブズ欲しい! でも、先月あれを買っちゃったしな…。もうクレジットカードの分割も使いまくっているし…」と言う女の子に、ショップの人が「じゃあ、もう一個方法があるけど、どうする?」と言うようなものですよね。そこで、どうしても欲しい! と思った女の子は、一回は我慢をしても、もう一回そういう誘いをされると、そこから崩れていく。一度入ったらもう平気になるしね。
――鹿島さんの『パリ、娼婦の館』『パリ、娼婦の街』を読んで印象的だったのは、一九世紀末にはじめてパリにデパートが出来たことの衝撃でした。注文しなくても、店に行けば商品がズラッと並んでいるという光景がはじめて起こった。女性たちは「お金があればこれが手に入る!」と思ったことで、衝動的に大金が欲しくなる…。
安野 「もっと良いものがあるよ?」という感じですよね。手袋だって、それまでは寒いからしていたのに、すごく贅沢な手袋を見てしまえば「わー!」と欲しくなっちゃう。――でも、当時は女性がお金を稼ぐ方法があまりなかった…。安野 あっても低賃金だしね。お針子さんとかばっかりで。それが今の日本と似ていると思います。
――安野さんは叙情画を描いた時も、昔の叙情画風ではなく、現代の叙情、現代の女性像を描きたいと言っていましたよね。「欲望の話」を描く場合、それこそ『pink』や『ヘルタースケルター』みたいに、現代を舞台に売春やモデル仕事を描くこともできたと思うんですが、直接的に現代のモチーフを選ばなかった。あえて違う舞台にしようと思ったんでしょうか。
安野 やっぱり今を舞台にして現実的に描いたら救いがなくなっちゃうから。読んでいる人が拒否反応を示す話になっちゃうと思って。格好良くしないで描きたいところもありましたし。時代をスライドさせることによって、描きたいことをストレートに描くことができる、というのはあります。
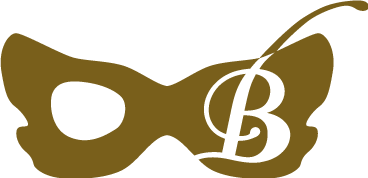
夜の卵の道具店
オフィシャルグッズはこちら





